こんにちは、ナカピラです^^

けどそれって売上のどのくらいの額を納税すればいいんだろう?
こんな疑問にお答えします。
この記事の内容
- せどりの確定申告で納める消費税の目安について
- 消費税をきちんと納税するためにやるべきこと
- 消費税・納税を2年間引き延ばす方法
- 読者さんからの質問:課税業者になるべきか?
この記事の信頼性
結論、稼いでいる利益率にもよるんですが売上の約5%と思っといてもらえれば大丈夫です。
年間の売上が1,000万円を超えると、翌々年に課税業者(消費税を納めないといけない業者)になります。
確かに最初の納税ではどれくらい納めればいいかわかりませんよね?この消費税をしっかり貯めておかないと春の納税シーズンに大変なことになります。
ぜひこの記事を読んで対策してください。
※ 正直、消費税やその他の税金についてのルールはとても複雑です。私は税理士さんに相談してようやく理解しましたが、ゼロから勉強するのはとても大変でした。売上が1,000万円以上あるのであれば、税理士さんを雇った方が後で悩まずに済むと思います。
≫【無料で紹介】せどりに詳しい税理士に相談する方法【やり方は2つ】
せどりの確定申告で納める消費税の目安について
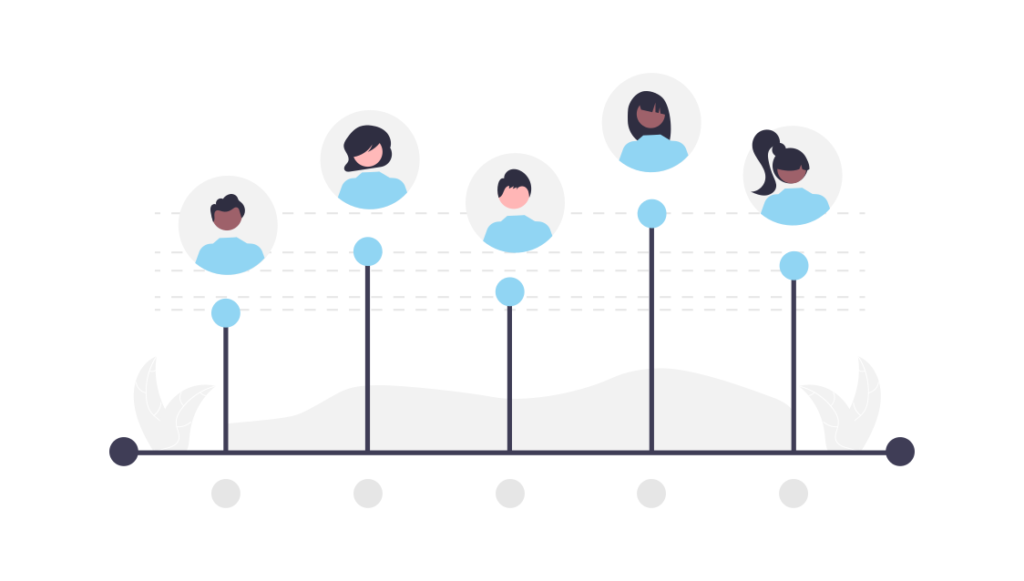
まずは消費税がどうやって計算されるのか知っておきましょう。計算方法は次の2つです。
- 原則課税
- 簡易課税
なんだか難しそうですよね。次の具体例をみて理解していってください。
消費税の計算方法①:原則課税の具体例
原則課税の公式
- 納める消費税額 = 受け取った消費税額 - 支払った消費税額
これを粗利率ごとに計算した結果がこちらの一覧表になります。
| 粗利益率 | 仕入額 | 受け取った消費税 | 支払った消費税 | 納付額 | 売上比率 |
| 15% | 1,979 | 300 | 180 | 120 | 4% |
| 20% | 1,814 | 300 | 165 | 135 | 4% |
| 25% | 1,649 | 300 | 150 | 150 | 5% |
| 30% | 1,480 | 300 | 135 | 165 | 5% |
| 35% | 1,315 | 300 | 120 | 180 | 5% |
| 40% | 1,150 | 300 | 105 | 195 | 6% |
(単位:万円)
一番右の売上比率を見てもらえるとわかると思いますが、平均で5%ほどですね。
さすがに30%以上を超えてくるともうちょっと上がりそうですが、基本は5%と覚えてもらえればいいと思います。
次に簡易課税を見ていきましょう。
消費税の計算方法②:簡易課税の具体例
簡易課税の場合
- 納める消費税額 = 受け取った消費税額 - (受け取った消費税額 × みなし仕入率)
原則課税と違うのは『みなし仕入率』というものがあります。
- みなし仕入率とは?:
これですね。さきほどの例と同じ、年商3,300万円で計算した結果が次の一覧です。
| 粗利益率 | 仕入額 | 受け取った消費税 | 支払った消費税 | 納付額 | 売上比率 |
| 15% | 1,979 | 300 | 180 | 60 | 2% |
| 20% | 1,814 | 300 | 165 | 60 | 2% |
| 25% | 1,649 | 300 | 150 | 60 | 2% |
| 30% | 1,480 | 300 | 135 | 60 | 2% |
| 35% | 1,315 | 300 | 120 | 60 | 2% |
| 40% | 1,150 | 300 | 105 | 60 | 2% |
(単位:万円)
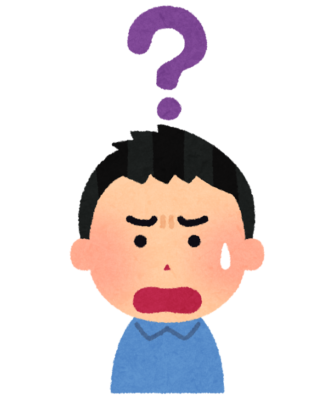
一見、こう思いがちですがそうとも限らないんです。
簡易課税がお得!なわけではない場合も
これは支払った消費税が少ない場合にのみ有効で、もし仮に仕入れを大量にしてしまい、支払う消費税が受け取った消費税よりも大きくなってしまうと逆に増えてしまうんです。
例えばこちらの場合、

- 受け取った消費税:300万円
- 支払った消費税:350万円
- 業種:小売業
- 原則課税 300万円 ー 350万円 = ▲50万円
- 簡易課税 300万円 ー (300万円 × 0.8) = 60万円
こうなると戻ってくる(還付される)はずの50万円が、逆に60万円支払わないといけなくなってしまいます。
つまり、受け取った消費税と支払った消費税のバランスによって計算方法を選択しないと損をしてしまう可能性があるわけです。
ただ、この場合は完全な赤字ですが。汗
消費税をきちんと納税するためにやるべきこと

毎月、売上の2%〜5%を積み立てましょう
- 年商5,000万円未満の方:2%
- 年商5,000万円以上の方:5%
年商5,000万円を超える方は【簡易課税】の計算方式は使えませんので注意してください。
やり方は簡単。
毎月売上が確定したら、その売上の2%〜5%を【消費税の専用口座】に貯蓄しておくだけです。
銀行はどこでも大丈夫、これで翌年の5月19日に耳揃えてきっちりと消費税を納めることができます。
やってない人は今からやっておかないと来年の春がキツくなります。今から準備するのが賢いですね。
消費税納付を2年間引き延ばす方法

年商1,000万を超えた翌々年には消費税を収めなければなりませんが、さらにもう2年伸ばす方法があります。
個人事業主から法人になる
”法人成り”と言われるものですが、個人の名前でやっていたビジネスを会社(株式会社・合同会社など)として登録し直す方法です。
年商1,000万円を超えた翌々年に法人成りすることで、さらに2年間は消費税を支払わないで済む”免税業者”になることができます。
法人成りするメリット
- 消費税を2年間免除される
- 節税できる【注)所得500万円以上が対象】
- 信用が上がる
消費税を2年間免除される
さきほど説明した通りですね。
法人成りしてから2年間は免税業者として消費税を納めなくても大丈夫です。
節税できる【注)所得900万円以上が対象】
個人事業主は累進課税(利益が大きければ大きくなるほど税金で持っていかれる)ですが、法人は法人税などを合わせた”34.62%”が税率になります。
そうですね。
課税所得を経費でなるべく減らし、支払う税金を減らすと言うイメージです。
収入によって税率変わりますので、可能ならば調整した方が良いでしょう。(こんなこと言うと怒られるかもしれませんが)
ちなみに7割もの法人が赤字申告で、わざと赤字申告する人もいるのは事実でしょう。 pic.twitter.com/OKM2mxwYd8
— なかピラ@プロ店舗せどらー&アフィリエイト3ヶ月目5桁達成 (@naka_pira) July 8, 2020
このように、900万円以上の所得になると個人事業主の場合、30%になります。
そうなると法人成りした方が節税できる場合もありますので、検討したほうが良いと思います。
信用が上がる
言うまでもなく、法人>個人よりも信用が高いので、取引先との関係づくりでも最初の印象が全然違ったりします。
銀行からの融資も獲得しやすくなるのもメリットといえるでしょう。
法人成りするデメリット
- 登記するのにおよそ25万円かかる
- 社会保険への加入が強制
- 会計・事務手続きが複雑になる
登記するのにおよそ25万円かかる
だいたい全て士業の方にお願いするとこれくらいかかりますが、自分でできる部分もあるためまだまだ下げることも可能です。
こちらの本につくり方が書いてますのでよかったら参考にしてみてください。
社会保険への加入が強制
これはメリットにもなりますが、強制という点と保険料が高いという点でデメリットに加えてみました。
ちなみに給料35万取るようにして年間の社会保険料を計算した時、120万円以上もの保険料を支払わなければなりません。
いくら厚遇されている保険とはいっても、やはりこの額は重くのしかかるのが現状です。
会計・事務手続きが複雑になる
会計処理が複雑になるため、税理士先生との顧問契約は必須です。
これも個人でできていた時とは違い、大きな手間ですのでデメリットといえるでしょう。
以上が法人成りするときのメリット・デメリットですが、復習すると法人成りを考えるタイミングは2つでしたね。
- 年商1,000万円を超えて納税業者になったとき
- 所得が900万円を超えたとき
よくよく考えて売上が伸びてきたらこちらを考えられてもいいのかもしれません。
読者さんからの質問:課税業者になるべきか?

先日、読者さんからこんな質問を頂きました。

私の回答は次のとおり。
結論:税金は恐れずに突っ走るだけ突っ走るのがおすすめ
理由はまだ7月で時間はたっぷりと残っており、その期間を何もせずただ眺めているのはもったいないからです。
税金は利益と預かっているお金以上にはかからない
税金は稼いだ純利益と預かっている消費税にしかかかってきません。
先に説明したとおり、支払い予定の税金をしっかりよけておけば何の問題もありません。
税金を支払うということは、それだけ稼ぐ力が付いているということ。出し惜しみせず、やれるだけ稼いだ方がいいでしょう。
この先が心配、あるいはもう満足!というなら話は別
ただ、そうはいってももう満足しているのであれば無理に頑張る必要もないと思います。
年商1,000万円に抑え、粗利30%越えならまとまったお金が手元に残ると思います。それこそさらに利益率が高ければ十分生活していけるだけのお金は稼げるはずです。
そうなると消費税を余計に払わないといけなくなる年商1,000万円はセーブしておいた方が良いのかもしれません。
年商1,000万円は月商84万で到達する
せどりはやればやるだけ経験と知識が身につき、腕がどんどん上がっていくビジネスです。
それこそ月商なら100万〜200万は数ヶ月で到達する人もいるほど。
年商1,000万円というととても大きな数字に見えますが、月商に置き換えたらそこまで大きい数字にはなりません。
税務署は全部は持っていかない
あとはご自身の判断になるかとは思いますが、税務署は利益全部は持っていきません。
稼いだ金額の3割ほどです。(他にも住民税や保険料がありますが・・・)
せっかく稼げる能力があるのにセーブしておくのはもったいないと私は思います^^
以上になります。
売上の5%、しっかり毎月積み立てといてくださいね!
それではまた^^
-

-
せどりに関わる税金について【納税額の目安とポイントについて解説】
続きを見る

